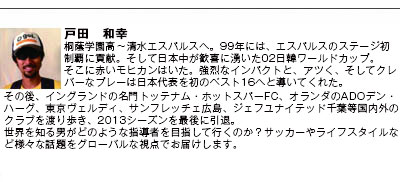戸田です、今日は。
今回で二回目の投稿になります。
何を書こうかと色々考えましたがせっかく怪我をしたので
怪我について書いてみようと思います。
人間、怪我をすれば当たり前のように病院に行って先生に診察を受けます。
必要な薬をもらったりリハビリに通ったりする事で回復を促します。
Jリーグのクラブにはみなチームドクターと呼ばれる専属の医師がいて
常に選手のコンディションを管理してくれます。
怪我をしたらクラブの規模によりますが直ちにドクターにみせて診断を受けます。
それから特別な治療が必要な場合は大きな病院にいったりします。
基本的に各クラブには治療を促すための医療機器があり
選手は毎日そこでチームトレーナーに身体のメンテナンスをしてもらえます。
これがJリーグにおける医療の実態です、非常に簡単ではありますが。
目線をシンガポールに移してこちらの実態はどうかと言うと
まず基本的にこちらの医療は病気をしても怪我をしても同じように、日本で言うかかりつけの病院に行かされます。
そこの先生はどの分野においても専門医というわけではなく必要に応じて専門医を紹介するというシステムです。
Sリーグの選手はリーグが提携・契約している病院にまず行かされます。
日本やヨーロッパのようにチームドクターはいなくしかもストレートに整形の専門医に診てもらう事も出来ません。
ここがまず一つ大きな違いです。
シンガポールに来てから紫外線の強さで目が痛くて開けられずぼやけて見えなくなりそうになった事がありました。
その時も同じ病院に行きましたが専門の眼科医を紹介すると言われましたがその日時は二週間後でした。
冗談みたいな本当の話です。
結局その時はシンガポールで知り合った薬局を経営している日本人の方に
眼薬などをいただいてなんとか治りましたがとにかく全てに時間がかかります。
プラス、チームには治療するための医療機器が全くないのでただマッサージを受けるくらいしかやれる事がありません。
ただただ時間だけが過ぎていきます。
ロンドンにいた時はわざわざバイエルンミュンヘンのドクターに診てもらいに飛んだ事があります。
スポーツ選手の怪我は時間が勝負なので日本もイギリスもオランダもすぐに診察を受ける事が出来ました。
シンガポールはそういう意味ではアスリートも一般の人も変わりない考え方なのかなと感じますし
保険でまかなえるその病院以外で診察を受けたり治療を受ける場合は自費でやってくださいという事になります。
なかなかスッキリしないシステムではあります。
怪我をして、今すぐ状態を知りたいとなっても、その病院に行って怪我をした時の説明をして、
では専門医を紹介しましょう、日時は一週間後ですとなります。
その先生は専門医ではないので何も判断出来ないんですね。
MRIを撮るのも一度その病院に行って紹介状を書いてもらわないと撮れません。
スポーツの医療はとにかく迅速で無駄がないものでないと治癒するのがどんどん遅くなります。
日常生活は出来てもスポーツは出来ない怪我はたくさんあります。
歩けても階段を登れてもサッカーは出来ないという事は当たり前にあります。
いかに今まで恵まれていたのか今痛感しています。
そんな中でも一生懸命コミュニケーションを取りながら仕方なく他の病院やフィジオテラピストを探して
自費でやってきていますが毎日当たり前のようにトリートメントを受けれた頃と比べれば遥かに質は落ちるし費用だけはかさみます。
プライベートの病院、日本人がやっているクリニックもありますが海外旅行保険に入っていればお金はかかりませんが
まさか自分で病院を探して行く事になるとは思っていなかったので。実費で受けると診察代だけでだいたい6000円します。
プラス薬をもらったり例えば検査をしたり注射を打ったりするとかなりの額になります。
二回目に目が見えなくなりそうになった時は診察と薬を処方してもらって二万五千円くらいしましたね。
足首の診察と一本注射を打ってもらった時は三万円以上しました。
なかなかビックリな額ですが今現在置かれた状況ではこれ以外に方法が見つけられませんでした。
フィジオテラピストに治療してもらう場合も超音波をしたり手技でほぐしてもらったり一時間で1万2・3千円します。
日本でも保険外診察を受ければこんな感じになるのかもしれませんが
今までプロチームに所属してそこで普通に受けれていた事がここではこんな感じになっているわけです。
これもまた経験と言えば経験になりますがなんとかより良い選択肢はないかと探してはいますが
おそらく日本に一度戻って全てを行う事以上に良いやり方は見つけられそうにないですね。
怪我はとにかく出来るだけ早く診てもらう事とそれが出来るまでは安静にする事です。
我慢して待つ事が苦手なのでだいぶ苦労していますが。
それではまた次回。