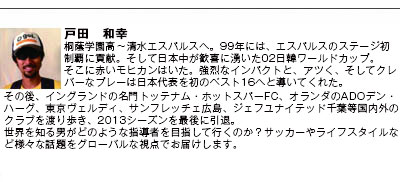またしても前回から間隔が空いてしまいました。
シンガポール特有ののんびり病に僕も罹ってしまったみたいです。
前回記事を書いたアルビレックス新潟シンガポールさんとの試合、結果から言うと3対1で勝つことが出来ました。
戦術的にはきちんと整備されたシンガポールの中では唯一のチーム。
ボールを「持つ」という事に関してはアルビさんに敵うチームはありません。
戦術的に大きな大きな差がある両チームの試合。
それでも今回うちが勝つ事が出来たのにはそれはそれで理由があると思っています。
勝てた理由と言うべきか、負けてしまった理由とするべきかは難しいところですが。
ボールを保持するという事はサッカーにおいて絶対的に必要な事です。
それはプレイしている人達が楽しむという意味で、充実感を得るという意味でも同様に必要な事です。
アルビさんのサッカーはボールを保持して動かす中、相手チームの疲労を誘い、
ライン間やポジションのズレを作りそのギャップを利用してスピードを上げて
突破していくという事になると思います。(あくまで僕の個人的な見方ですが。)
自分達のチームとしてのスタイルを築き上げることがサッカーに限らずまず大切だと思うし
これがないとただのリアクションサッカーになり、サッカー本来の持つ楽しさからは離れていくことになります。
自分達のスタイルを持てた上で、今度は相手との力関係による試合の運び方や駆け引きが必要になりますが
自分達に備わっているべき必要なものが足りないと
ただひたすら相手チームのやりたい事に振り回される結果になります。
残念ながらまさに自分のチームがそれに当たります。
戦術的にとても乏しいシンガポールではアルビさんのやろうとする、
今世界では普通に行われている動きながらのサッカーに対抗する術は基本ありません。
少し前に首位を走るタンピネスというチームとの試合を見ましたが、
ただペナルティエリア前に4人ずつのラインを2つ置くだけで
ボールに合わせて横に素早くスライドする事もなくただミスを待つだけの守り方。
サイドで数的不利を作られ散々突破されていました。
センターバック二人が日本人ですが話をしても戦術的な苦労をはっきり感じました。
補足するとアルビさんが縦横上手く使いながら素早く効果的なボールの動かし方をしたわけではなく
ゆっくりゆっくり次を探しながらボールを動かしていてもそういう展開になっていました。
そして例に漏れず我々のチームも同じ展開になりました。
マイボールになってもただ前へ前へと攻め急ぐ為あっという間にボールを失うし、
とにかく細かいポジション修正が出来ないので、
たとえゆっくりボールを動かされても必ずどこかに穴が空いてしまいます。
そんな中で自分に出来る事は何か、これはもう走るしかないんです。
ボールを奪うチャンスをひたすら待ちながら、前後左右にアプローチとカバーをし続ける。
ただし行き過ぎるとそれがきっかけで逆にバランスが崩れるので我慢を強いられる。
とにかく勝ちたい一心で愚直に愚直にやり続けました。
プラスこれは失礼な言い方になりますが、
アルビさん側のクオリティや試合運びにも問題があったおかげで勝つ事が出来たんです。
本来であれば間違いなくアルビさんが勝たなくてはならないほど両チームにはチームとして大きな差がありました。
それでも勝ててしまうのがサッカーの面白いところで醍醐味なのかもしれませんが。
運良く一点リードしたタイミングで、これは僕が勝手にやりましたが
前線一枚だけ残して中盤を横並びの5枚に変更しました。
ただでさえポジショニングや戦術的に乏しい上、足が止まってしまったらもうお終いです。
ということで人数を増やして縦パスを入れるスペースを消す事と
横のスライドする労力を減らして、相手の焦りを誘うようにしました。
これはアルビさんが長いボールを使わないという事もあっての考えでしたが、
幸いにアルビさんの焦りを誘う形となりカウンターで更に一点追加して勝つ事が出来ました。
が、あまりに効率が悪くプロと呼ぶには頭を使わないサッカー、
シンガポールではフィジカルとロングボール頼みのサッカーがまだまだ普通。
アシストの記録もつかずとだいぶ先端からは遅れています。
その今ある枠自体を少しでも変えようという事でクラブとリーグに声をかけてもらい
シンガポールに来たわけですが今のところは残念ながら何も変わっていません。
日々行う練習から取り組み方まで難しいなと感じる事が今日まで続いてきました。
ここにはここのスタンダードがあり、それは例えば日本であったり韓国であったり
またはヨーロッパと比較すると相当に違います。
子供達は勉強勉強で外で遊ぶ子供をまともに見た事がないくらい、この国は学歴社会で競争が激しいようです。
スポーツ自体があまり親しまれていないように見えるしもちろんサッカーをする子供も少ない状況です。
スポーツやサッカーがこの国にとってどれだけ重要視されているのか。
心身を育む意味でもスポーツの持つ意味は大きいと考えますが、
シンガポールではまた違う考え方があるように見えます。
試合をしてもお客さんがまるで入らないSリーグ。
この国の今ある形と照らし合わせて見てみると、自分なりにではありますが見えるものがあり、
社会とスポーツの関係性など勉強になるのは事実です。
これからこの国とこの国のスポーツがどうなっていくのか、自分の予想と照らし合わせながら眺めていき、
それをまた自分の今後の材料にしていけたらと思います。